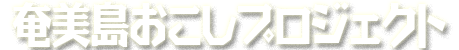みつばちと農業
養蜂、つまりみつばちの飼育を行うことですが、多くの人々は蜂蜜の採取を目的とした仕事だとイメージしているのではないでしょうか。養蜂は養鶏と同様に畜産業に分類されていますが、経済的な効果から見ると、蜂蜜などの直接的な生産物から得られる経済効果よりも、農作物の受粉媒介によって発生する経済効果のほうが遥かに大きいのです。日本養蜂はちみつ協会による報告(1999年)によれば、蜂蜜、ローヤルゼリー、蜜蝋等による国内生産額は72億円であるのに対し、農作物の受粉媒介によって得られる作物総生産高は3453億円に及び、規模にして50倍、割合においては98%を占めているのです。
みつばちは農業と大変深く関連しています。みつばちが受粉媒介する農作物は、イチゴ、メロン、サクランボ、スイカ、トマト、ナス、キュウリ、カボチャ、ゴーヤ、タマネギ、柑橘類、リンゴ、モモ、ナシ、ウメ、マンゴー、ブルーベリーなど枚挙に暇がないほどで、かつて無かった作目が次々と導入されてきたこの半世紀近くの間に、その役割は一層大きいものとなっています。つまり、私たちはみつばちの働きに助けられて、はじめて様々な種類の農産物を口にすることができるようになったのです。
一昨年(2011年)発表された国連環境計画(UNEP)の報告書によれば、世界のミツバチの数は「過去50年間で45%近く減少」しており、過去10年で激減しているのは主に北半球で、欧州ではミツバチの10~30%、米国では30%、中東では85%が死に絶えてしまったそうです。さらに今世紀に入っては、アジア・オセアニア、アフリカ各地でもミツバチの減少が起きており、日本についても「25%の養蜂家が蜂群の消失に直面した」と言及されています。原因は複合的だとされ、農薬や大気汚染、寄生虫、環境破壊、花の咲く植物の減少、養蜂家が減ってしまったことなどが挙げられています。そして、みつばちを始めとする受粉媒介者の減少を放置すれば、多くの種類の植物は実りをもたらす事が出来ず、人類は食糧危機に直面すると警告しているのです。報告書の主執筆者の一人、スイス蜂研究センターのペーター・ノイマン博士によれば、「この半世紀ほどの田舎や農村地帯の変化は、野生の蜂や他の花粉媒介生物の衰退の引き金となりました。(中略)もっとも重要なのは、野生の蜂の生息数を回復させるために、周囲のランドスケープをより適切に管理しなければなりません」と述べています。
「奄美島おこしみつばちプロジェクト」では、野性の在来種であるニホンミツバチと畜産対象であるセイヨウミツバチの飼育を行なっています。これは奄美地域の主要産業である果樹栽培を中心とした農業生産の振興に寄与するため、みつばちの有用性を検証するための実験として始めたものです。奄美地域は亜熱帯性の温暖な気候に恵まれ、年間を通じて様々な花々が咲いているにもかかわらず、養蜂群の規模はごく僅かです。一方、同様の気候風土にある沖縄県では7300群のみつばちが飼育され、全国上位10県のうち5位にランクされています。こうした差異の要因はどのような点にあるのかについても調査したいと考えています。
また奄美地域の農業において、虫媒花に依存する作目のポリネーターは野性の在来種であるニホンミツバチなどの昆虫類であるなら、その収穫は自然環境のもたらす生態系サービスによって支えられていることになります。前述のペーター・ノイマン博士の言うように、農地やその周囲に蜜源や花粉源となる植物を育て、野性のポリネーターの衰退を防がなければならないでしょう。